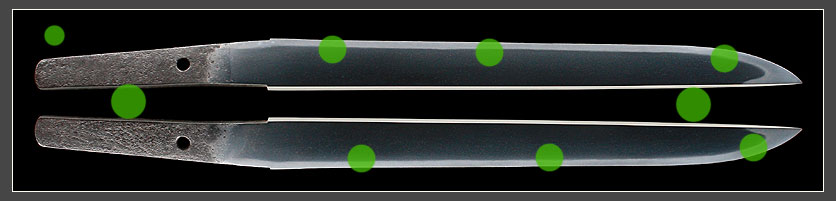
極)末延寿
| 時 代 | 室町時代 |
|---|---|
| 長 さ | 23.5cm / 七寸七分六厘 |
| 反 り | 内反り |
| 元 幅 | 2.2cm / 七分三厘 |
| 元 重 | 0.5cm / 一分六厘 |
| 附 属 | 白鞘 / 銀無垢二重ハバキ |
| 鑑 定 | 保存刀剣-日本美術刀剣保存協会 |
| 価 格 | 案内終了 |
形状 平造、庵棟、内反り付きやや小振りの姿
鍛 小板目約(つ)み、やや流れごころ、地沸つく
刃 細直刃、焼き刃低く、小沸付き、匂い口締まる
帽子 わずかにたるみごころで入り、小丸に返る
茎 生ぶ、栗尻、鑢目不明、目釘孔一つ
■ 鎌倉時代末期より肥後国菊池において隆盛を見た延寿一派。その追尾を飾るのが、末延寿と称される刀工集団です。
本刀はその末延寿と鑑定された短刀で、流れごころのある強い鍛えに、小沸の付いた直刃を焼いており、伝統に則した作風は好感を覚えます。 また小振りな姿は引き締まってまとまっており、やや強めに付いた内反りは、時代の姿を顕著に表しています。
■ 近年錆身で現れた本刀に 上質の工作を施しました。傷や朽ち込みなど無く、このまますぐに伝統の魅力を知ることが出来ます。
無銘ながらも 末延寿の魅力を十分に秘めた優品です。
干将庵 / 2017年5月08日
〒362-0059 埼玉県上尾市平方1506-5 電話 / FAX: 048-780-3074 IP電話: 050-7507-0599 info@kanshoan.com

